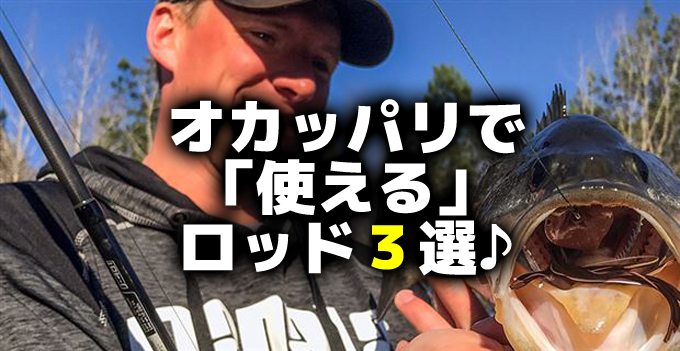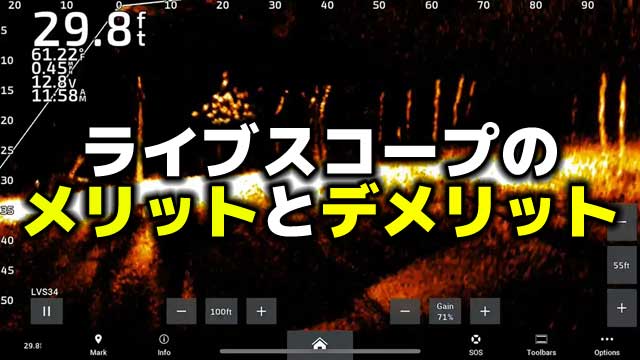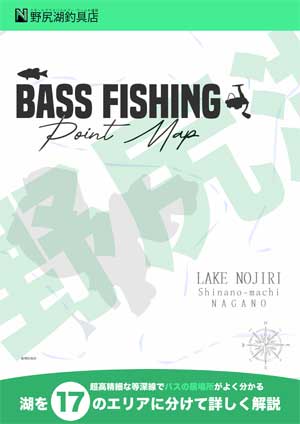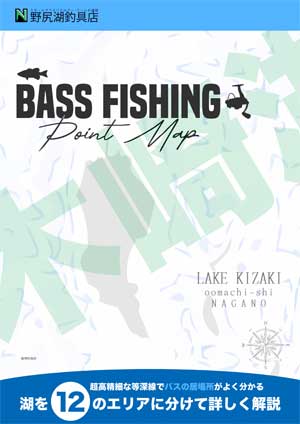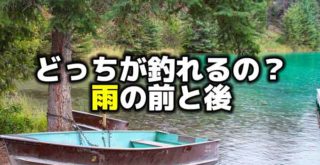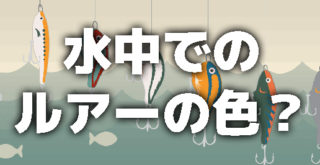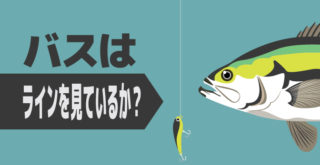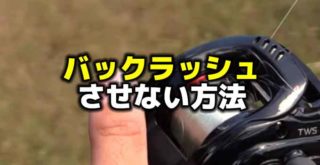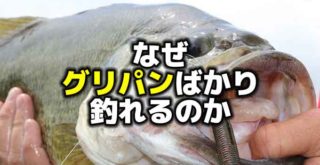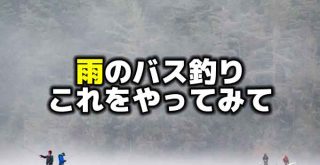フックの錆はこう防ごう!

釣りをしている以上、私たちと錆(サビ)とは常に背中合わせの状態です。フックが錆びるということは釣果を求めるにあたっては致命傷というほどの現象ですから、なんとか防いでいかなければなりません。しっかり錆対策をしましょう。
こんにちは!店長の小山です!
本日は海外サイトより、”Knock The Rust Off! How To Avoid Fishing Hook Rust”という記事を引用してご紹介いたします。
引用先:shopkarls.com ”Knock The Rust Off! How To Avoid Fishing Hook Rust”
釣りという水遊びをしている私たちにとって、何かが「錆びる(さびる)」というのは常に隣り合わせの現象です。
防波堤によくある、石原裕次郎が片足を乗せるキノコ状のやつ(ビットと言います)、あれなんかはだいたいどこに行ってもサビッサビの真っ赤っかです。
湖やリザーバーで見かける作業船、例えば物を運ぶ台船や砂を掘り出す浚渫船(しゅんせつせん)などは塗装をされていれば目立ちませんが、下地の鉄はかなり錆が浮いていることが多いんですよね。
この例は申し訳ありませんが他人事のようなものですので気にならないのですが、釣り人である私たちにとって自分事として起きる最大のトラブルが「フックのサビ」ですよね。
他にもスプリットリングやスピナーベイトのブレードなど、錆びるものはいくらかあるのですが、フックのサビは釣果に響くものとしてはダントツの致命傷となります。錆びたフックは極端に折れやすく刺さりにくいという状態で、とてもじゃありませんが新品の時の性能は維持できていません。
ものぐさな私は、久しぶりに開けたフックケースの中のフックがすべて錆びてケースの中が茶色い粉まみれになっていたことがあります。
現場でそれが判明した時は意識が飛びそうになってしまいましたが(笑)、残念ながら、水分をまとったまま放っておけば、フックは錆びます。
しかしながら、現象にはすべて原因があるということですから、その原因を取り除くことによって、フックのサビが発生させるのを大幅に遅らせることができます。
この記事は、アメリカのタックルショップ「Karl’s Bait & Tackle」のブログ記事で、フックのサビについて解説されています。
アメリカ人は豪快なイメージですが「フックのサビなんて気にしないぜ~ガーッハッハッハ!」なんていうアングラーはほとんどいません(笑)
せっかく買ったフックを使わずしてダメにしてしまわないよう、知識をつけておきましょう。
フックのサビ対策、していますか?
学校の理科の授業で習ったことをおさらいすると、鋼の鉄粒子が酸素と湿気に触れて、鋼が腐食した結果として錆が発生するということでした。 酸素はこれらの粒子を酸化させるきっかけとなり、水酸化物は鉄粒子と反応して含水酸化鉄または錆を形成します。
釣りが終わった後、ルアーをタックルボックスに戻すところから、錆の問題は発生します。 タックルボックスのフックに残っている湿気は、そのフックに錆を発生させ、その錆は他のフックに山火事のように広がり、ルアーにダメージを与え、ボックス内に茶色い汚れを残す可能性があります。
私たちが釣りをしているときは身の回りには常に水がありますので、ルアーやタックルボックスを乾いた状態に保つのは難しい話です。 雨の中でルアーを交換することもありますし、波がボートのバウを越えて入り込み、水がストレージの中に入ると、湿気がタックルボックスの内部にまで忍び込むことがあります。
ルアーをどうやって錆から守ればいいのか?
次に、フックの錆を防ぐための鍵として、タックルボックスに保管する前に、すべてのルアーとフックが乾いていることを確認することです。 雨の日に釣りをしたのであれば、家に帰ったらタックルボックスを開けて、1日中外に出し、すべてのルアーとフックを乾かすことです。
塩もフックが錆びる原因になります。そのため、海や汽水域で釣りをするときは、釣りが終わるたびに、フックから塩分を真水で洗い流してください。 淡水での釣りであればそこまで心配する必要はありませんが、塩を含むワームと同じボックスにフックを保管しないように注意してください。
錆を防ぐフックの保管方法
タックルボックスに入れておくことで水分を吸収し、フックの錆を防ぐアイテムもあります。 タックルボックス内に入れる湿気吸収材の1つで最も安いものは「つまようじ」です。つまようじは、木を窯で乾燥させたものですので、水分をよく吸収します。 「綿棒」をボックスに入れるのも、フックから湿気を吸ってくれます。
しかし、タックルボックスから湿気を吸収し、フックの錆を防ぐための最良の方法は、各ボックスに2つ~3つの「シリカゲル ドライパック」を入れておくことです。 通販でシリカゲルパックを購入してもいいですし、ビーフジャーキーの中にあるもの、薬箱の中に入れるようなもの、下駄箱に入れるものでも代用できます。

つまようじや綿棒でもひとまず湿気取りとして使えるんですね。知りませんでした。
つまようじはワームに刺してフックの身切れ防止に使ったり、キャロライナリグのシンカー留めに使ったりしますし、綿棒はリールにグリスを塗ったりロッドガイドの汚れを取ったりしますから、タックルボックスに入れておいてもおかしくはないアイテムですからね、これが錆対策として有効だというのであれば、2重の意味で使えるアイテムということになるでしょうか。
最近ではソルトフィッシング用に防錆(ぼうせい)加工されたフックというのも発売されていますので、もしかしたらバス釣り業界でもこれから錆びないフックが普通になるのかもしれません。
しかし、限られた予算内で釣りを楽しみたいのであれば、安いフックでも自分が気を付けることでその分の予算を他のことに回すことができますから、覚えておいたほうがいいですよね。
つまようじと綿棒は確かに安いですが、最高の効果を発揮するシリカゲルパックも実際は高価なものではありませんから、余裕があればシリカゲルをタックルボックスやフックケースに入れておくといいでしょう。
先日、雨の野尻湖でご一緒したDeeep STREAMのけんでぃさんもシリカゲルで対策し、リグチェンジする時は傘をさしてタックルボックス内への雨の侵入を防ぐという念の入りようでした。
こういうところはやはり見習いたいものです。
このほか、そもそもタックルボックス内に余計な水分を入れない方法としましては、特にラバージグやスピナベ、バズベイトなどのラバースカート系などがそうなのですが、ルアー交換の時にしっかり手で「ブンッ」と振って水気を切ってから交換すること、これだけでも結構、乾きやすさが違うと思いますので、やってない方は、やってみてくださいね。
ということで無駄な社内会議とタックルボックス内はできるだけ「さんか」しないようにしましょう(笑)
それではまた。
毎度ありがとうございます!
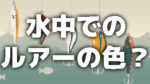
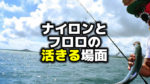
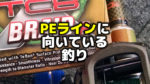


![:[D] 錆びで全滅!?雨の日のフック救出作戦 - ◆ DeeeP STREAM ◆ ディープストリーム](https://nojiriko-fishing.net/wp-content/uploads/luxe-blogcard/5/53c406ed77957092fcdf9aab299694fe.jpg)
 http://deeepstream.com/2020/07/03/protecthooksfromrusting/
http://deeepstream.com/2020/07/03/protecthooksfromrusting/