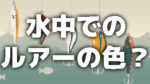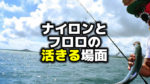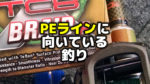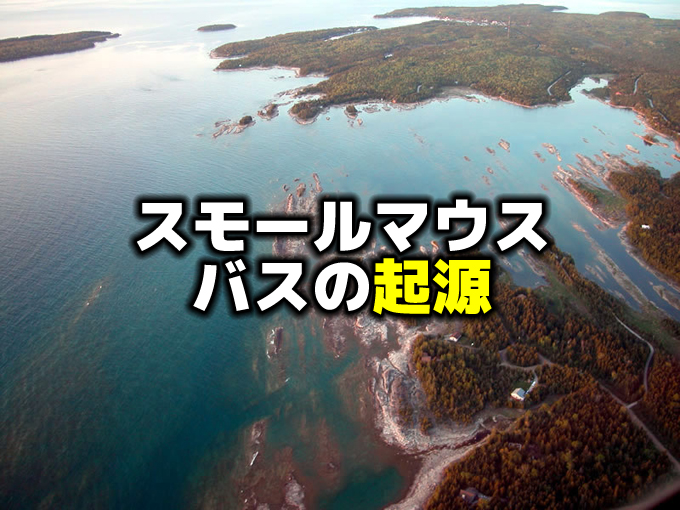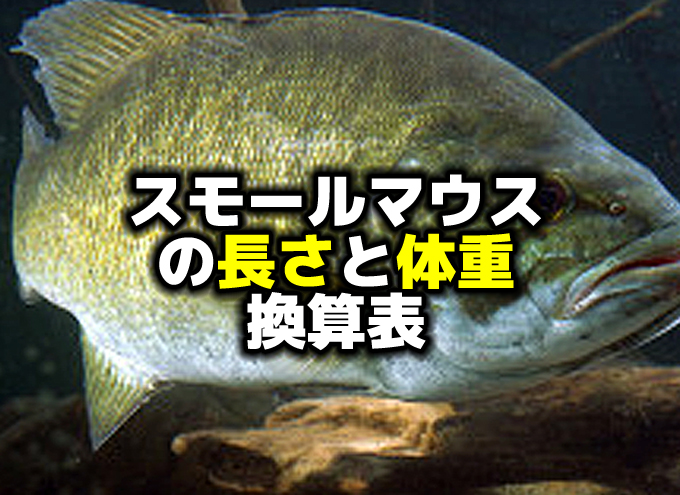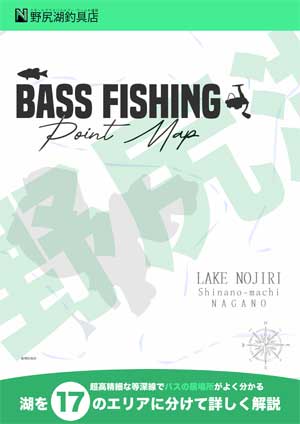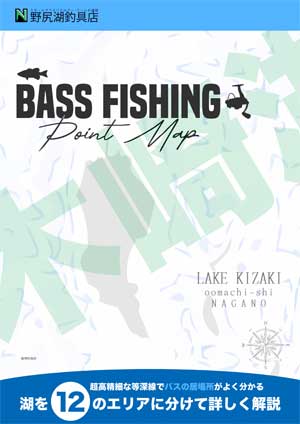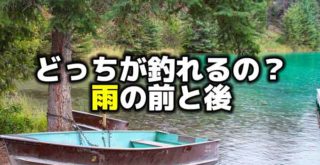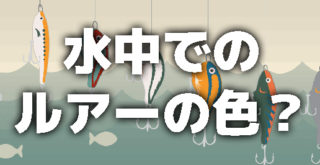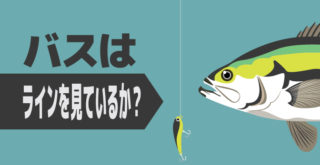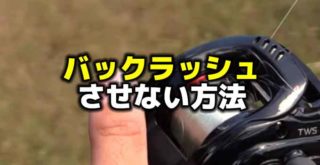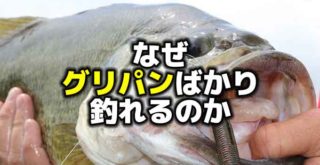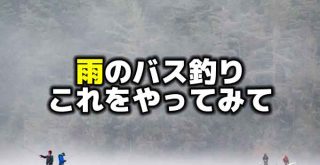【小ネタ】魚はノドが乾かないの?

釣りを愛する私たちは、魚にとっていちばん必要なものは水だということをよく理解しています。しかし「魚は水を飲まなくてもいいのか?」という疑問をもったことはありませんでしょうか?
こんにちは!店長の小山です!
本日は小ネタですが、「魚はノドが乾かないのか?」という疑問についてお話ししたいと思います。
私たち人間や動物は、水を飲まなければ生きていけませんよね。
バス釣りをしている私たちアングラーにとって、魚に最も必要なものは水だというのはごく当たり前のように理解しているはずですが、ちょっと待ってください。
「魚って、水を飲まなくても生きていけるの?」
こんな疑問を持ったことはありませんでしょうか。
もしあなたが、そんな疑問を持ったことがあるのでしたら、私と同じですね!
私は子供のころからその疑問を持っていましたが、解決することはできませんでした。
しかし、私も大人になり、インターネットが普及した現代になったことで調べることができるようになりました。
その時に覚えたことを今回はお話しさせていただきます。
子供さんも大人の方も、私と同じ疑問を持つ方がこの記事でスッキリしていただければ嬉しく思います!
浸透圧(しんとうあつ)を知っていますか?
浸透圧というのは、液体が同じ濃さになろうとバランスを取ろうとする現象です。
ざっくりとした説明になってしまいますが、たとえば濃さのまったく違う2種類の食塩水を並べて、その境い目にめっちゃ小さな穴がいっぱい開いた壁を作ったとき、その境目ではお互いの水が同じ塩分濃度になろうとして、濃い方の水が薄い方の水を吸収していきます。
このときに掛かる力を浸透圧と言いますが、この現象そのものを指していることも多いかと思います。
これが浸透圧のざっくりとした説明で(合ってると思いま)す。
魚の場合は自分が住んでいる水中の水と、自分の体内にある水分がありますので、その境目の壁となるのは皮膚とエラということになりますね。
淡水魚と海水魚は浸透圧が違う
海水と淡水では、魚の外側にある水の塩分の濃さがだいぶ違いますが、そのあたりはどうなっているのでしょうか?
淡水魚の場合は、体内の塩分よりも外にある水の方が塩分濃度はかなり低いです。
ですので、先ほどの浸透圧を利用することで、身体の外側から水分を吸収することができます。
また、魚も人間と同じように、生きるには適度な塩分が必要なため、魚のエラにある特殊な細胞によって体内の塩分が調整されているようです。
海水魚の場合はその逆です。
魚の体内の塩分よりも海水の方がはるかに塩分が濃いので、浸透圧により海水魚は体内からどんどん水分を奪われているようです。
海水魚が泳いでいる動画を見ていると、ときどき口を大きく開けているのを見たことがあるかもしれません。
実はこの時、魚は水をたらふく飲んでいるんだそうです。
魚が口から飲んだ水はエラを通らないので、塩分は調節されていません。この場合の余分な塩分は肝臓で調節されています。
じゃあ、海水魚はノドが渇くの?
私たち人間は、激しい運動をしたあとや寝起きのとき「のど乾いた―」と言って水を飲みますが、これは意識してやっている行動ですよね。
海水魚が口を開けて水を飲んでいるのは分かっていますが、それが果たして喉が渇いたと意識しているかどうかまでは分かっていないようです。
魚が人間と同じような感情をもって水を飲んでいるのか、それとも純粋な本能がそうさせているのかが科学的に判明するにはまだ時間がかかりそうですね。
海から川をのぼる鮭はなぜ死なないのか?
淡水魚を海に放すと死んでしまいますし、海水魚を淡水に放すと死んでしまいます。
これは、魚が急な浸透圧の変化(塩分濃度)に耐えられないためです。
しかし、鮭のように海水から淡水に移動する生活サイクルの魚もいますし、シーバス(スズキ)のように個体によっては淡水エリアまで進出するものもいますよね。
鮭の身体の構造は、海水に住んでいる時は大量の水を飲み、淡水に住んでいる時は大量の尿を輩出するように切り替えているため、死なないのだそうです。
また、海水と淡水が川でつながっているとしても、淡水と海水の境目がスパッとはっきりしているわけではなく、徐々にその濃さが変わります。
鮭は川を上るときにその境目エリアを超ゆっくり泳いで、その水に徐々に慣れていくのだそうです。
他にもスズキやクロダイ、ウナギなどなど、海水でも淡水でも生きることができる魚はいると思いますが、何らかのかたちで浸透圧を調節する機能が発達しているということです。
結論、魚の気持ちはわかりません
調べてみた結果、魚も人間や他の動物と同じように、生きるためには水分を取らなければならず、なかでも海水魚は口から水を飲むことまで分かりました。
しかし、私たち人間と同じように「あーのど乾いたー」といって飲んでいるかどうかまでは分かりませんでした。
これについては果たして本当に科学が解明してくれるのかも正直なところ、分からないと思います。
魚とお話しできない限りは…。
このブログを書いている2023年現在、魚と会話する方法は残念ながらありません。
しかし、だからこそ、魚という謎多き生き物は私たちにとって魅力的であり、いつまでも私たちの興味が尽きないのだと思います。
どんなに優秀な学校を卒業した人にも魚の気持ちは分からないという点で、魚は私たちに平等に接してくれています。
私たちが好きな釣りという趣味は、人によっては野蛮な行動だと批判されることもありますが、ルアーやアプローチを研究し、魚と釣りを通して会話を試みていると考えると、人類としてはるかに先進的なのかもしれません(笑)
一生かかっても解けることがないかもしれない謎というのは科学者にとっては屈辱かもしれませんが、その謎そのものを楽しむ釣りというものをずっと楽しめたら、私たちはそれだけで幸せですよね。
でも本当は、釣り人こそ、魚の気持ちが知りたい人種ですけどね(笑)
それではまた。
毎度ありがとうございます!