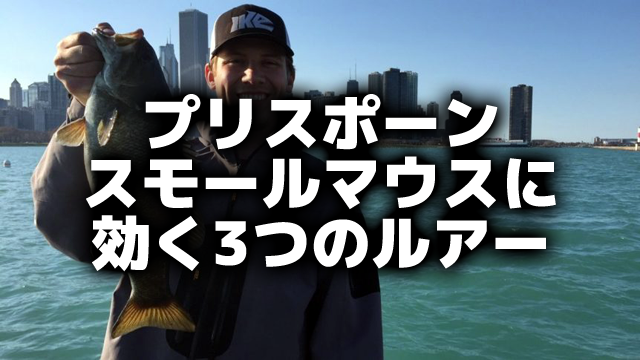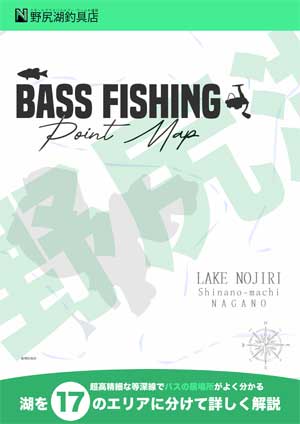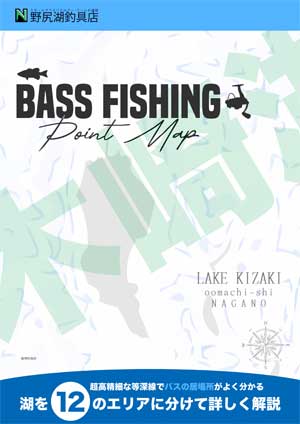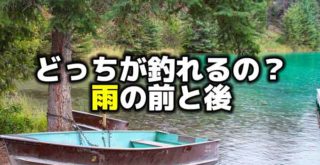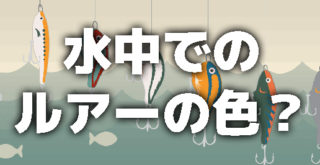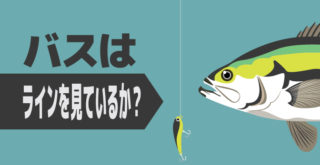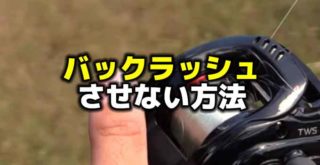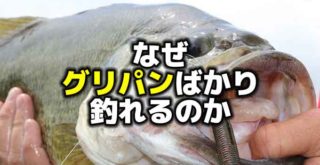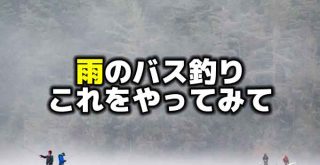冬のスモールマウスバスはベイトフィッシュを見ている
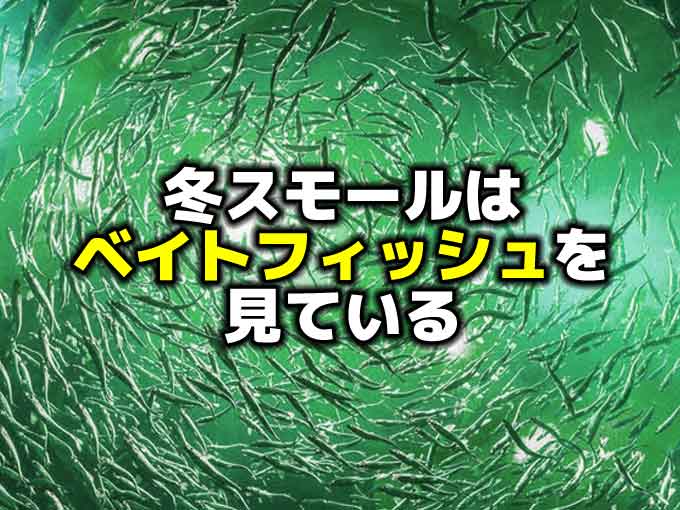
バス釣りの基本のひとつに「マッチザベイト」という言葉があります。しかしこれは、今バスが食べているものを知らなければならないことを意味します。さて、冬のスモールマウスバスは何を食べていると思いますか?
こんにちは!店長の小山です!
本日は海外サイトより、”Shad before 'dads in winter”という記事を引用してご紹介いたします。
引用先:bassmaster.com”Shad before 'dads in winter”by Stephen Headrick|November 22, 2009
冬のスモールマウスバスは何を食べているのでしょうか。
バス釣りの基本原則のひとつ「マッチザベイト」を行うためには、バスが食べているものを知る必要があります。
まあそれを知っていても、冬に禁漁になってしまう野尻湖、結氷してしまって実質的に釣りにならない桧原湖ではあまり役には立たないのかもしれません。
それでも、スモールマウスバスを釣るのが大好きな者のひとりとしては知っておきたいものです。
冬は釣りにならないと言っても、冬に近い季節ならまだスモールマウスバスの釣りができますしね。
さて、すでにタイトルを読んでらっしゃる皆様においてはすでに答えが出ているようなものなのですが、そうです、ベイトフィッシュですよね。
これは冬に限らず、スモールマウスは秋ごろからベイトフィッシュに着く傾向はかなり強くなりますので、この難しい季節、良い情報であれば知っておいて損はありません。
この記事は、アメリカバスマスター公式サイトのコラム記事で、アメリカのスモールマウスバスフィッシングの第一人者スティーブン・ヘドリック氏が、冬のスモールマウスバスのためのルアーについて解説してくれています。
これを読んで、わずかしかない冬場のスモールマウスバス釣りに役立てましょう。
冬に使うのはザリガニではなくベイトフィッシュ
私が寒い季節にスモールマウスバスを釣りたいときは、ほとんどの場合、ザリガニ系ルアーではなくシャッド(ベイトフィッシュ)系のルアーを使用しているのがお分かりかと思います。理由は単純です。バスは、低水温期になるとザリガニよりも魚を多く食べるためです。
冬になると、ザリガニはクマなどの動物のように冬眠とまではいきませんが、かなりの無気力状態になり、ほとんど活動しなくなります。つまり、バスはそれらを食べる機会が少ないということです。バスはある時点で、ザリガニを見かけなくなったと感じたとき、もうザリガニを探すのをやめます。春が終わり、再びザリガニを多く見かけるようになれば、私もザリガニ系ルアーを復活させます。
ではこれが現場レベルでどうなるのかと言えば、実際にはほんの少しの変化でしかありません。ルアーに茶色や暗い色のものを使う代わりに、ベイトフィッシュ系の明るい色のルアーを使います。
そして、そのルアーを操作するときには、それをザリガニよりもベイトフィッシュのようなアクションになるようにします。つまり、ボトムを這わせることが少なくなり、泳がせたり漂わせたりすることが多くなります。私はベイトフィッシュとは言ってもボトム付近でゆっくり使うこともありますが、ザリガニを模倣しているときのように這ったり、非常にゆっくりなジャンプをさせたりすることはありません。
それはまた、私のルアー選択すらあまり変わらないことを意味します。私はよくラバージグを使います。それが暗い色ではなく、シルバー、ホワイト、ライトグレーといった色のラバージグになります。
バスがクランクベイトにバイトしてくるほど高活性だと感じれば、ベイトフィッシュパターンが成立します。もちろん、バスがそれほど(水温的に)高活性であるということは、ザリガニも穴から外に出ている可能性があり、ザリガニパターンが成立する可能性もあります。
私が心掛けている取り組みのひとつは、より細いラインを使うということです。冬、ザリガニではなくベイトフィッシュ系ルアーを使う場合、通常はヘビーカバーまわりで釣りをするということではないため、細いラインが使えるというわけです。また、バスは低水温で無気力なので、それほど激しいファイトもしません。また、冬の水はかなりクリアでもあります。
それらはすべて、より細いラインが有利であることを意味します。
もちろん、細いラインの素晴らしいところは、通常はより多くのバイトが得られるということです。そしてこの時期、バスが他の季節ほどフィーディングをしないのですから、私は得られるバイトはすべて取りたいのです。
これであなたはまた、より良いスモールマウスアングラーになるはずですね。

アメリカでは、バスのナンバー1ベイトはやはりザリガニということだそうです。
ここで「えっ、ザリガニって冬眠するんじゃないの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
一応、定説ではザリガニは冬眠すると言われているかもしれませんが、実際はかなり動きは遅くなるものの、冬眠はしないようです。
ただし、ここが重要なのですが、普段のザリガニの生息地である岩場からは姿を消し、泥底のエリアに移動して、穴を開けて泥の中で過ごしているんですね。
泥底エリアに冬のザリガニが集結するというのは、バスにとっては朗報かもしれません。
日が当たったりして水温が上がれば、動きの遅いザリガニが巣穴から這い出して来るのですからね。
冬場のバスが泥エリアで釣れるのにはこのような理由もあるのでしょう。
ザリガニは500種類以上いるそうですので、そのうちのどれかは冬眠するのかもしれませんけどもね。
私の個人的な印象とすれば、冬場だからといってスモールがザリガニ系からベイトフィッシュ系のエサにスイッチのオン⇔オフのように切り替わるような実感はあまりありません。
私のよく行くフィールドでは、常にボトム系のバスと中層系のバスがいて、どちらがでかいのか、どちらが釣りやすいのかを実験?実証?しながら釣っている感じです。
ですので、この記事から受ける私への教訓としては、実験をやめるな、バスは何を食べたいのか見極めよ、ということでしょうか。
えっ、違うでしょって?
いえ、それがですね、寒くなるとリグチェンジやルアーチェンジするのも面倒臭くなってしまうので、「あと一投したらルアー替えるか…」といいつつずっとあと一投してしまう私にはいい教訓なんです(笑)
みなさんもぜひ、バスの好きな物を見極めること、冬場こそ面倒臭がらずにしっかりやりましょうね!
それではまた。
毎度ありがとうございます!

 https://www.bassmaster.com/blog/shad-dads-winter
https://www.bassmaster.com/blog/shad-dads-winter