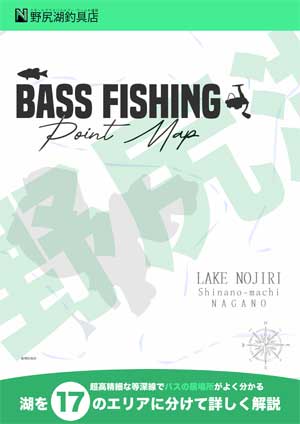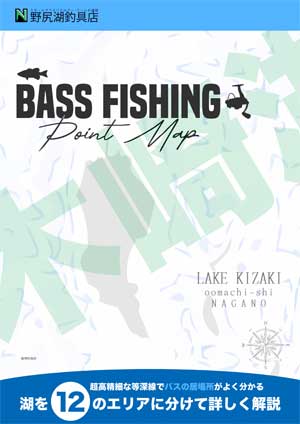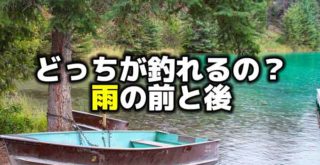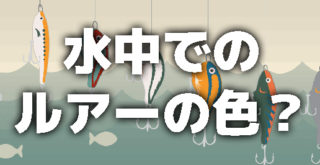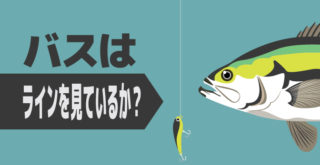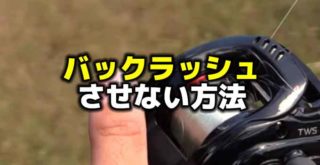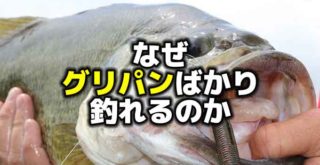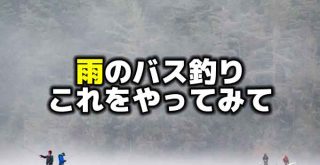9月のバス釣りはこう変化します

9月に入るとなんとなくバス釣りも後半戦かな、という気分になります。これは、これまでの夏のピークのころから釣りがガラッと変わるのを何となく感じているからではないでしょうか。この変わり行く釣りを予習しておくことで、秋全体の釣りが良くなるようにしましょう。
こんにちは!店長の小山です!
本日は海外サイトより、”Tips for tackling bass in September”という記事を引用してご紹介いたします。
引用先:bassmaster.com ”Tips for tackling bass in September”by Andy Crawford September 2, 2013
最初にちょっと野尻湖の話になってしまいますが本編はスモールマウスの話ではありませんのでぜひ最後までお読みくださいね。
9月になりますと、野尻湖へよく行く私としましては、バス釣りは後半戦に突入のイメージになります。
野尻湖は4月下旬に解禁されて、11月上旬で禁漁期間に入ってしまうため、釣りができるのは6か月間のうち残り2か月ほどということになります。
解禁のちょうど半分となるのが7月下旬ごろになりますので厳密にいいますともう後半戦に入ってはいるのですが、なぜ9月に入って後半戦になるという感覚になるのかといいますと、このころから釣りがガラッと変わってしまうからなんです。
避暑地である野尻湖もさすがに夏は暑いのですが、これが9月にもなると朝晩の気温が一気に下がり、かなり涼しくなります。
これが湖の表水温を下げるためか、バスのレンジがかなり上下動するようになるんです。
これうなると「野尻湖が後半戦に入ったな」となるのですが、こういった変化はおそらく野尻湖に限らず、どのタイプのフィールドにも当てはまることなのではないでしょうか。
秋は難しいというのは合言葉的に使われる言葉ですが、それがあらかじめ分かってれば、少しでも予習ができていれば、秋全体の釣果が良くなるかもしれませんよね。
この記事は、アメリカバスマスター公式サイトのコラム記事で、9月に入ってからのバス釣りの変化について解説されています。
9月のバスたち、また水中ではどんな変化が起きているのでしょうか。
早速読んでみましょう。
9月のバス釣りに取り組むために
9月は夏の暑さからようやく秋の涼しさに変化しはじめる移行月です。サウナ状態から脱却できることは素晴らしいニュースのように聞こえますが、多くのバスアングラーが苦労する時期でもあります。
問題は、バスがディープにある夏の溜まり場を離れて動き回るために、探しにくくなることです。
「歴史的に見ても、バスフィッシングのトーナメントの記録を振り返ると、9月のウェイトはかなり下がっています」とバスマスターオープンを戦ったプロのサミー・バークスはB.A.S.S.タイムズの取材で言いました。 「バスはどんどん浅い方まで移動し始め、そして分散するのです。」
「これは厄介な状況です。午前中にバスを見つけた場所でも、午後になるともういません。」
バークス氏は、これの分かりやすい例として、テキサス州アミスタッドレイクで数年前の9月のトーナメントで起きたことを語ってくれました。
「初日は27ポンドをウェイインしましたが、最初の2時間でそれを揃えました。 2日目に同じ場所に行って2ポンドしか釣れず、1位から16位まで落ちました。3日目は17ポンドを釣って最終的に10位で終わりました。」
問題は、ベイトフィッシュが1つの場所に留まっていないことです。
「これはすべてベイトが関係しているんです。 ベイトフィッシュが動き回っていて、バスも一緒に動いている状態です。」
この予測不能さに対する解決策は、ルールブックを捨てるということです。
「基本的には、プラクティスの続きだと思ってください。 ベイトフィッシュを見つけたとしても、2時間後には消えてしまう可能性があります。」
「パターン化するのはほぼ不可能です。」
チャンスを最大限にするためのカギは、ルアーの変更を素早く行うための準備です。
「私はデッキに20本のロッドを置いています。 トップウォーターからボトムを釣るためのルアーまで、あらゆるレンジをカバーするさまざまなルアーを用意します。」
「ロッドに4種類のクランクベイトを結んでいることもありますが、9月のバスの動きは分かっているつもりなので、いつでも他のルアーに変更する準備ができています。」
多くの場合、アングラーは水面でのボイルを狙っていますが、バークスは魚探の使い方が彼の戦略の大部分を占めると言います。
彼はまた、「シャッド(アメリカのベイトフィッシュの一種)がまだ主なベイトフィッシュであり、間違いなくそれを見つけるのがメインです。」と言います。 「フラット、段差、オダのどこを探すにしても、ますはシャッドを見つけます。」
バークス氏によると、ベイトフィッシュもバスも気まぐれで定期的に動いているのだと言います。
「ラン&ガンしかありません。 オープンマインドで、魚が姿を消したら、あなたも動く必要があります。」
しかしバークス氏は、その移動は長距離を走ることを意味するものではないと言います。そうではなく、そのエリア内の他の水深を見て回って、近くにいるバスの群れを見落とさないようにするということです。
「クリーク内で釣りをしているのなら、ジグザグに見て回ります。 ディープにいたのなら、4.5メートルレンジを見てみます。それからもっとシャローも見てみます。」
また、風はアングラーが魚の居場所を突き止めるための重要な要素です。
「かなり風の強い日であれば、ベイトフィッシュは、湖岸の風が当たる側のバンクやブレイク、またはウィードエッジに集中する可能性があります。つまり、湖の風上側は無視して、風が吹きつけるエリアに集中すればいいのです。」

9月からバスを釣るためにはベイトフィッシュに集中しなければならない、ということはよく言われていることですので分かるのですが、ベイトフィッシュにはたいした意思決定もなく移動をし続けているようですから、バスを見つけるのも大変だという話でしたね。
私も本当にこれには賛成で、また野尻湖の話になってしまって申し訳ないのですが、野尻湖には「美味しそうなカバー」というものがほとんどないんですね、また、すり鉢状の湖で地形変化もめまぐるしい変化というほどのものはないため、ベイトフィッシュの動きが本当に自由気ままな感じになると思います。
そのため、この記事に書かれている通り、「風」というものがベイトフィッシュの行動を左右するとても大きな要素になるんですよね。
もうひとつ忘れてはいけない賛成意見としましては、それほど遠くに移動するわけではないということです。
この記事では別のレンジを探してみると書かれていましたが、これがまさにその通りで、例えばさっきまでフラットの8mラインにいたバスもベイトも、釣り流しているうちにいつの間にか全くいなくなることがあるんです。
もちろんそれではバイトがなくなるのでエリアを移動しようかな、となるのですが、そのためエレキでちょっと移動してからエンジンを掛けようとすると、その間にまたベイトとバスの群れを見つけるとこが結構あるんですよね。
なんだ、みんな隣の9mラインに行っただけか、となるんです。ただしフラットエリアの水深1mの差というのは横の距離にするとまあまあありますので注意が必要なんですけどね。
まったくいなくなってしまったようで案外近くにいる、ということも覚えておかなければいけないと思いました。
これまで調子のよかった、シェードやディープのブレイクや流れ込みといった夏の代表的なピンポイントから徐々にバスは抜けてしまい、ベイトフィッシュに着くようになるようですから、これまでのマニュアルですとか先入観というものは一旦しまって、今日のバスは、今のバスはどこかということに集中したいものですね。
そのカギは、オープンマインドですね。
それではまた。
毎度ありがとうございます!