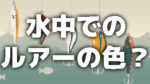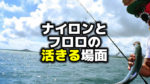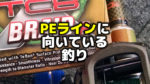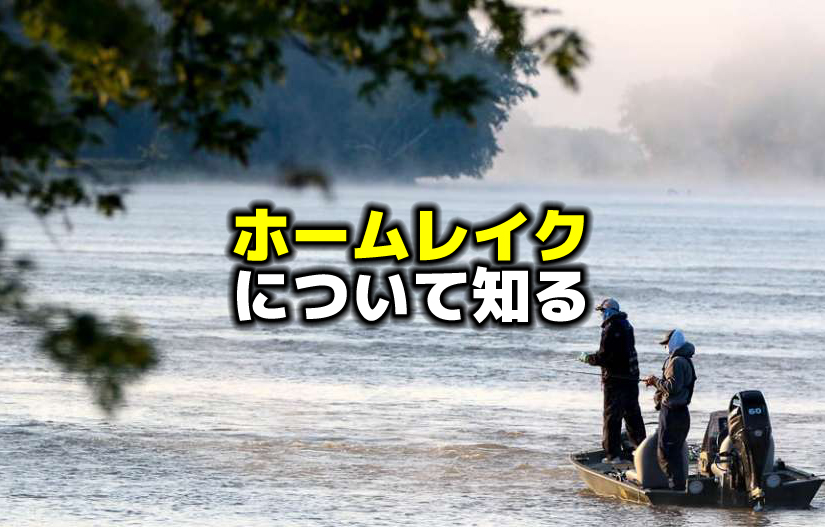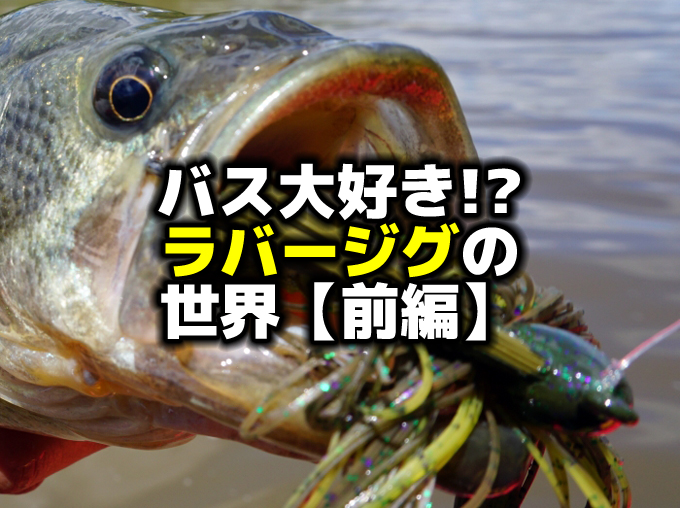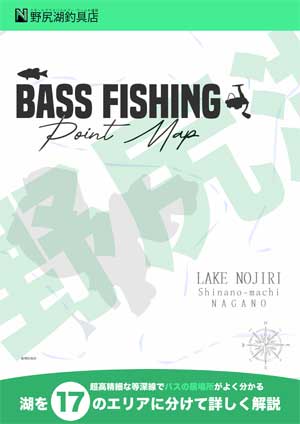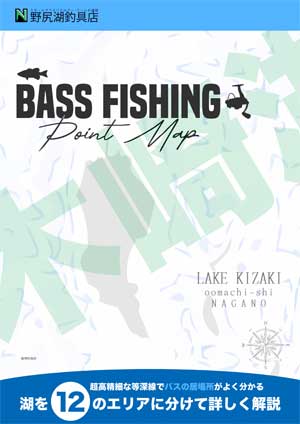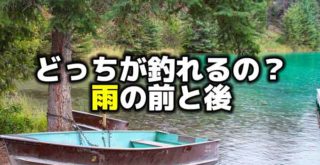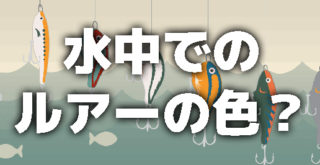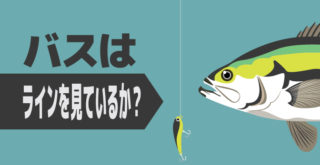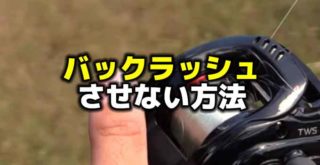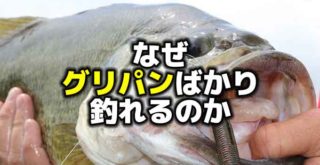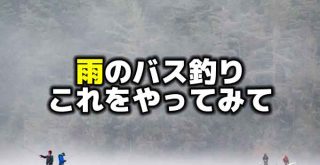オープンウォーターのベイトフィッシュに付くバスを釣るには

こんにちは!店長の小山です!
本日は海外サイトより、”Open Water Bass”という記事を引用してご紹介いたします。
引用先:bassfishing-gurus.com ”Open Water Bass”
ブラックバスという魚は基本的には、カバーや地形変化に居着く魚ですよね。
回遊性が強いと言われているスモールマウスバスでも、基本的にはそういうものを横目に見ながら行動していると思います。
バスに限らず、肉食の動物というのはだいたいが、余計な体力を使わないように、獲物に気付かれないようにギリギリまで忍び寄って仕留めるという行動をすると思います。
バスも自分の存在を隠すため、少なくとも目立たないようにするためには、物陰に隠れたり地形を利用する方が都合がいいはずですよね。
しかし、そんなことをまったく気にしていないグループもいます。
自分の存在がどうとかはもう気にせず、完全に開き直ってベイトフィッシュをストーキングしているグループです。または日頃のフィッシングプレッシャーを避け、アングラーの裏をかくように行動しているとも言われています。これはラージもスモールも関係なく存在しているんですよね。
この手のバスを釣るのは非常に厄介です。例えばナチュラルレイクやリザーバーなどでその傾向は違いますし、天気や時間帯によってもベイトやバスの居場所が変わってしまうためです。
出来ればそんな厄介なバスを相手にしたくはありませんが、たとえば秋という季節、またカバーの極端に少ないフィールド、常にフィッシングプレッシャーの強いフィールドなどでは、そんなバスを相手にするしかない状況もあるかと思います。
ベイトフィッシュに付くバスを釣る方法は、なんとかマスターしたいものなんですよね。
この記事は、アメリカのバスフィッシングをメインとした釣り専門メディア「bass fishing gurus.com」の記事で、ベイトフィッシュに付くバスをどう釣ればいいか、解説してくれています。
オープンウォーターの釣りが苦手な方は、ぜひ読んでみてください。
水面をよく観察する
水面を観察するとは言っても、どうやらベイトフィッシュがバスに追われてボイルが起きていないような場合はどうするか。そのまま水面を観察したとしても、多くの場合、見えバスを釣るのは見えていないバスを釣るよりも難しいものです。 ベイトフィッシュが追われて水面から飛び出しているようなときだけオープンウォーターのバスを釣るようにします。見えバスにこだわると、チャンスを逃してしまうかもしれません。
表層に魚がいると判断するには
まずしなければならないのは、多くの魚がいるレンジを突き止めることです。 魚は1日の間に上下に動くことも覚えておいてください。 私の考えでは、魚のレンジが3メートルより深い場合、魚探で探すことになります。 水面直下にいる魚は魚探で見つけるのはかなり難しい場合が多いので、魚探に映る魚の群れが消えたら、水面直下に来たと考えます。 しかし、だからと言ってこのオープンウォーターのどこにいるかを知るには、依然として難しい問題を抱えたままです。
バスがカバーからいなくなるのはなぜか
ベイトフィッシュを追ってオープンウォーターを回遊しているバスとは言っても、通常はクリークチャンネル、ディープブレイク、桟橋、橋脚、その他の地形変化をに依存しています。 バスがディープの表層に浮いたり、カバーを離れて回遊することはあるかもしれませんが、状況にもよりますが、これらの魚はたまたま付き場から外れているだけです。
それでは、カバーや地形変化の恩恵を受けるエリアからバスが離れる原因は何でしょうか? 答えは、ほとんどが食事のためです。 それさえわかっていれば、かなりポジティブな考え方や攻め方でこれらの魚にアプローチすることができるはずです。
速い釣りをしよう
地形などに関係していないオープンウォーターのバスには、ルアーを落とし込む範囲がかなり広いため、チャンスは多いと言えます。 ロングキャストをすれば、クランクなら最初から最後まで有効なゾーンを通せるためかなり有効になります。 また多くの場合、こういった魚を狙うには、スピードのある速い釣りをすることが効果的だと私は考えます。 速く釣りをするということは、オープンウォーターにおいてより多くのキャストができることを意味しますし、スピードは魚を反応させる強力な引き金になると思います。
そのための私のお気に入りのテクニックの1つは、ヘビースピナーベイトをロングキャストし、素早くリトリーブすることです。 スピナーベイトの利点は、カウントダウンすることでヒットゾーンが見つかるまであらゆるレンジを探れるということです。
バスがカバーにいないと判断したら
バスがいつもの地形変化やカバーを留守にしているようだと判断したら、隣接するオープンウォーターをしばらく時間を使ってベイトフィッシュを探してください。 夏から晩夏にかけて、これらの回遊魚ねらいは安定したパターンと言える釣りであり、多くのアングラーが見落としがちです。
地形変化から離れたオープンウォーターの釣りというのは確かに不安になるものですが、こういうエリアで速い釣りをするということは、効率は良いわけですから、釣れる確率は変わりません。

オープンウォーターの釣りが苦手な方の多くは、普段からカバー撃ち中心の釣りをされている方かもしれません。
私はオープンウォーターの釣りをすることの方が多いものですから、カバーにスキッピングでルアーを送り込むと言った技術にはまったく自信がありませんので、きっとその逆ですよね。
と言っても、私がオープンウォーターの釣りが得意とは言っていないわけですが(笑)
この記事で大事だなと思うのは、ベイトフィッシュやバスの活動を目で見るなり魚探で探すなりしてから釣るということであって、決して当てずっぽうで釣らないということだと思います。
確かに、目で見えるボイルだけを釣ることや、魚探に移るベイトやバスだけを釣るということは、釣りの範囲は狭くなり効率的ですし、いると分かっている魚を釣るという信頼感がありますよね。
また、この記事に書かれていたことで思ったことは、ちょっと離れた表層の魚は魚探に映らないということです。
ワンキャスト分も離れたら魚探には映りませんよね。(サイドスキャンなどがあれば別ですが…)
実際、魚探に移るベイトフィッシュの群れを見ながらエレキを踏んだり風に流されていると、ベイトの群れがせり上がって来て、そこでいなくなる(消える)ことがありますが、その直後にボートの周りワンキャストの範囲ぐらいの距離でボイルが起きたりします。
これは実は私がボイルフィッシュを狙う時に楽しみにしている魚探映像で、ボイルが起きなくてもベイトが表層に追い込まれている証拠ですから、どんな沖であっても表層系ルアーをとりあえずキャストするタイミングなんですよね。
これは最初にも言った通り、スモールもラージも関係なく起きると思いますので、どんなに沖でこれが起きても躊躇なくルアーを投げ込むことが重要かと思います。
沖のベイトフィッシュに付くバスを釣るのは本当に厄介なのですが、ボイルの気配を少しでも事前に感じることができれば激アツですから、ディープの釣りをしつつ、水面や魚探を常に気にしていくようにしましょう。
私もボイルに頼らなくても大丈夫なくらいディープの回遊バスの釣りが上手になりたいですから、もっともっと練習しなくては!
それではまた。
毎度ありがとうございます!