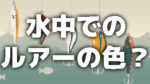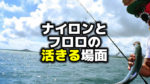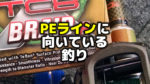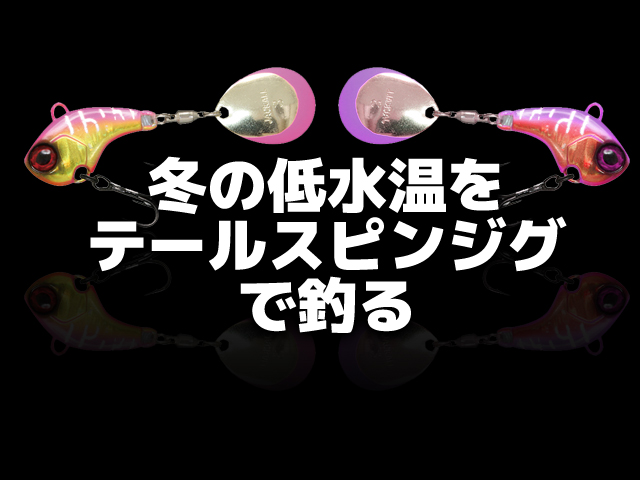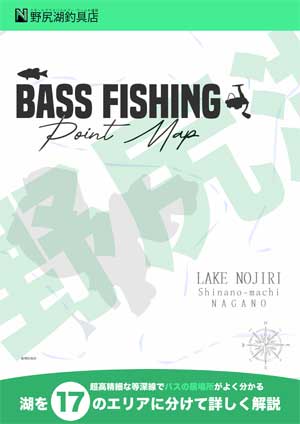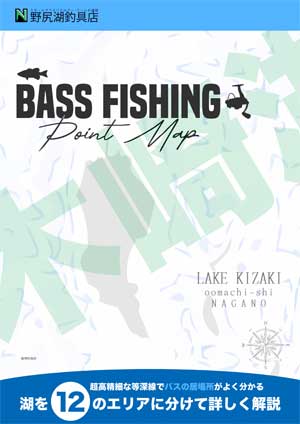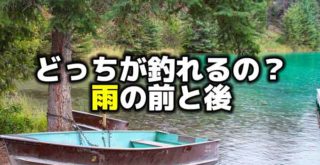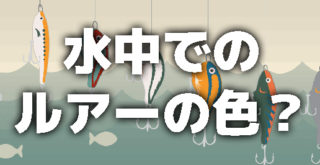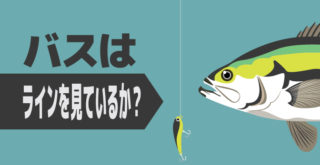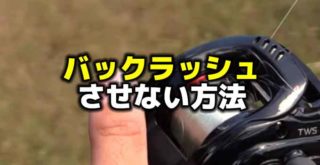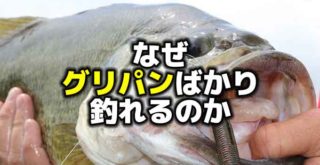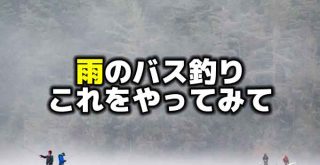秋のバス釣りはベイトフィッシュを追え

秋のバスというのはベイトフィッシュの動きにあわせているようです。ということは、ベイトフィッシュの動きを知ってしまえば、あとは簡単にバスは釣れ…ないかもしれませんが(笑)、ベイトフィッシュの動きを知るということは非常に有効なはずです。
こんにちは!店長の小山です!
本日は海外サイトより、”Using Baitfish Activity To Find More Fish”という記事を引用してご紹介いたします。
引用先:shopkarls.com ”Using Baitfish Activity To Find More Fish”
「春ワンド、夏は岬で秋ベイト」という言葉があるように(?)、秋のバス釣りというのはベイトフィッシュがキーとなる季節と言われています。
この秋という季節、人間の感覚で言うと単純に春夏秋冬、四季のうちのひとつという感じですが、水中の世界では、最高水温のピークを越えたあたりから冬になるまでという、意外と長い期間を指しているようです。
具体的に言えば、水温のピークを越える8月中旬ごろから水温が下がり切る前の12月中旬ぐらいと言えるのではないでしょうか。
これは地域にもよりますので完全な定義づけは難しいのですが、秋は意外と長いということには変わりないかと思います。
私を含め、秋のバス釣りが苦手という方はつまり、ベイトフィッシュの捉えどころが難しいといいますか、ベイトフィッシュに支配されたバスを釣るのが苦手ということになるのだと思います。
この意外と長い期間を苦手としてしまうのですから、なかなか厄介な問題を抱えていることになりますね。
なんとかベイトフィッシュの特性をつかみ、秋のバス釣り対策と出来ないものでしょうかね。
この記事は、アメリカのタックルショップ「Karl’s Bait & Tackle」のブログ記事で、秋のベイトフィッシュの行動を知り、バス釣りに活かそうというものです。
いったいどんなことが書かれているのか、読んでみることにしましょう。
秋のベイトフィッシュの群れはどこに

夏の終わりから初秋にかけて、クリークやメインリバーの上流にあるフラットエリアにシャッド(淡水ニシンのなかま=アメリカの代表的なベイトフィッシュ)が集まります。 バスの魚影が濃いフラットエリアを直接見つけるのというのはなかなか難しいので、シャッドを食っているバスが釣れるパターンを求めて、クリークじゅうを走り回って探すことになります。
この時期にシャッドを見つけるのに最適なスポットは、クリークチャンネルに向かって泥底からチャンクロックに変化するバンクです。 ベイトフィッシュはほとんどの場合、フラットエリアの水面にシャッドが活動しているのが見えるほど浅いところにいるはずです。
ベイトフィッシュの群れの理想

大きなシャッドの群れがいるスポットは魅力的に見えますが、ベイトフィッシュの数が多すぎるという可能性もあります。 これは、特に夏の終わりから初秋のクリークやメインリバーで問題になります。 エリア内のバスの量に比べてシャッドが多すぎる場合、食べ物が豊富なため、バスを釣るのが難しくなる可能性があります。 こういったエリアでも何投かしてみるのは良いと思いますが、思う通りに釣れない場合は、そこを離れ、まばらなシャッドの群れがいるエリアを探す方が良いでしょう。
クリアレイクのベイトフィッシュ
水深のあるクリアウォーターのハイランドリザーバーでは、夏の終わりから秋にかけては岬沿いにシャッドの群れが見られます。 水温が下がってきたことで、ベイトフィッシュとバスはシャローへ動こうとします。 したがって、ボートを水深約7mあたりに置いて、水深3〜6メートルにいるベイトフィッシュを追うバスを狙うようにします。 ベイトフィッシュはめったに水面まで出ないので、通常はこれらのベイトフィッシュは魚探を使って探すようになります。 魚探でベイトフィッシュの群れを見つけたら、通常は多くのバスがサスペンドしているのも見えるはずです。

シャッドというベイトフィッシュというのは日本にはいないので完全一致とはいかないかもしれません。
しかし、ワカサギヤオイカワなど日本の代表的なベイトフィッシュたちも、フィールドによりますが、それぞれ秋には秋の行動をするかと思います。
例えば私が知っている野尻湖や木崎湖のワカサギは秋になると、それまで水深8m前後のバンクからフラットエリアに広く分散していたものが、もう少し深いフラットエリアの水深10mから15mあたりに集結し、巨大な群れを作るようになります。
同じワカサギという魚でも、これが急深リザーバーになるとまた別の行動をするのではないかと思います。
秋という季節が意外と長いというのは初めにお伝えした通りですし、しかもその年によっては夏を引きずったり、逆にすぐに寒くなったりと、ばらつきがあったりもしますよね。
こういうことがあるので厄介だったりもするんです。
しかし地球の自転と公転による日の長さというものには毎年ほとんど差がなく、立秋や秋分の日がやってくるタイミングは変わりません。
人間の体感するその年の季節感のズレがあるために、なおさら惑わされてしまう部分もあるのだと思うのですが、野生動物の営みというのは、実は毎年だいたい同じような行動をしています。
つまり、一度ベイトフィッシュの行動パターンを見つけてしまえば、毎年同じようなタイミングで同じような場所にいるもので、あとはそこにどれだけバスが着いているかの違いくらいなのではないでしょうか。
ただし、近年の琵琶湖のように、メインのベイトフィッシュがアユやブルーギルからワカサギに変わってしまうなど、大変な変化もあります。
こんな時は大変に惑わされてしまうものでしょうけども、それも一度つかんでしまえば毎年同じようなパターンに落ち着くのではないかと思います。
やるべきことは、そのフィールドのベイトフィッシュの行動を、まずはパターン化することですよね。
しかしながら、実際問題として、ベイトフィッシュを見つけるまでは良いんです。
そこから先の、どのようにして食わせるか、どんなリグやアクションが有効なのかについては、やってみなければ分からないところがあり、それこそが難しい部分でもあると思うのですけどもね。
まあ私にとってみれば、イージーな季節などというのもないわけで、いつも難しい難しいって言ってますから(笑)、そういうところを楽しんでいるわけで、難しい部分が残っているのはむしろ歓迎なんですけどね。
バス釣りがそんなに簡単だったらこんなに夢中になってないよという方は多いのではないでしょうか。
それでもぜひ、この秋、ベイトフィッシュの動きからの秋バスを完全攻略しようではありませんか。
それではまた。
毎度ありがとうございます!