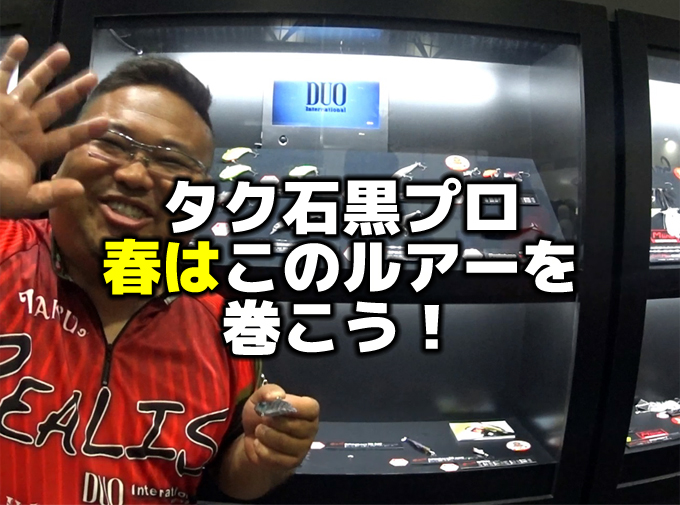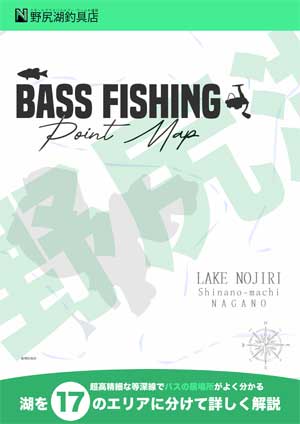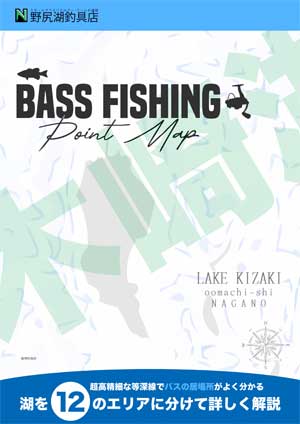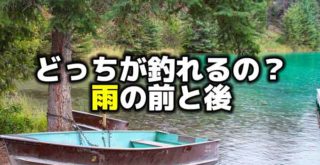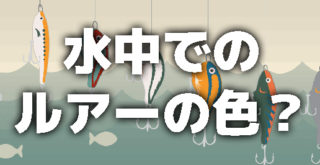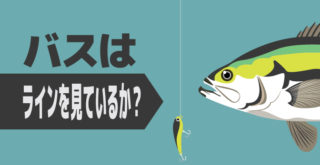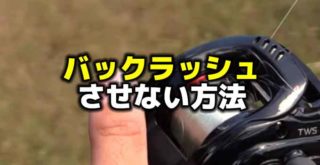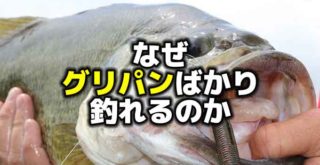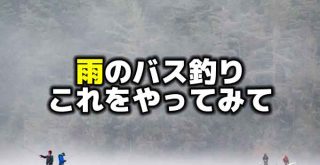【バス釣り】見落としがちな最重要アイテム!シンカーの選び方と使い方をわかりやすく解説

バス釣りをしている中で、おそらくですが一般的に最も過小評価されているアイテムが、シンカーではないでしょうか。しかしシンカーひとつにもいくつかの役割があり、ここにこだわることで確実に釣果に結びつくものだと思います。
こんにちは!店長の小山です!
本日は小ネタですが、バス釣りで使うシンカーについてお伝えさせていただきます。
バス釣り用のシンカーとは?
バス釣りをしている中で、おそらくですが一般的に最も過小評価されているアイテムが、シンカーではないでしょうか。
たしかに、直接バスの口に作用する唯一のパーツであるフックに掛ける予算を妥協するべきではありません。ラインも、バスとアングラーをつなぐ大事な命綱です。それに比べれば、シンカーというのはサブ的なアイテムということになるでしょう。
しかし、シンカーの役割を分解してみると、いくつかの役割を担っていると思います。
- キャストのしやすさ…シンカーがあることでキャストの飛距離が伸びたり、コントロールがしやすくなる
- ルアーを沈める…釣りの効率を良くするため、ルアーがボトムまで沈む速さを上げたり、ルアーの沈む速さを調節する
- ボトムを感じる…キャストした先のボトムの質が泥なのか砂なのか石なのかなど、ボトムの質を見分ける
- ボトムで踏ん張る…ボトムでルアーが動きすぎないようにアンカー(イカリ)の役割をする、逆に踏ん張り過ぎないことを求められる場合もある
ざっとこんな感じかと思います。そしてこの1~4のそれぞれに、その度合いに適した形状や重さというものがあります。
そうなると、その選択肢はフックやラインの数にも並ぶ量になります。数多いなかから正しい選択をするのは大変かもしれませんが、シンカーにこだわることは、あくまでも間接的にですが確実に釣果にもつながるもので、軽視すべきではないアイテムだと思います。
シンカーの種類や特徴
それでは次に、私がよく使うシンカーのうち2種についてのご紹介などをさせていただこうと思います。
もしかしたらかなり個人的な考えに偏っていることがあるかもしれませんが、その際はご容赦くださいませ。
中通し式シンカー
バス釣りで主に使われている中通し式シンカーといいますと、バレットシンカーとラウンドシンカーだと思います。
バレットシンカー
バレットシンカーは片方が尖っている形をしているもので、尖っている方がロッド側、太い方がワーム側になります。テキサスリグ、キャロライナリグで使います。
この形状により、ウィードのスリ抜けが非常に良くなっています。濃いウィードの中へリグを入れていきたいようなときはこのシンカーが活躍します。
ラウンドシンカー

中通し式のラウンドタイプシンカーはウィードのスリ抜けはよくありませんが、逆にウィードの上にリグを乗せていきたいときなどはこちらのタイプを使います。
私が木崎湖のウィードがあるところでライトキャロをやる時はこのタイプのシンカーの1~1.8グラムを使っています。
ブラスシンカー

中通し式シンカーの中でもブラス(真鍮=しんちゅう)でできているものがあります。
ブラス素材は比重が低く、同じウエイトだと鉛やタングステンに比べて大きくなってしまうためか、最近はあまり見かけません。
しかし、このシンカーの良さはガラスビーズと一緒に使った時のサウンドにあります。テキサスリグやキャロライナリグで使った時にシンカーとビーズがぶつかり合うことで「チキチキ」という非常に大きな音を出します。この音は他の素材では出せません。
この音はザリガニがハサミで敵を威嚇する時の音に似ているということでバスが反応すると言われていますが、本当かどうかは分かりません。ただ、この組み合わせが大好きで、こればかり使っているというアングラーさんも一定数いることも事実ですよね。
ダウンショットシンカー
ダウンショットリグで使われるシンカーには大きく分けて3種類あり、それぞれを使い分けることで高い効果が得られます。
ティアドロップ型
ダウンショットシンカーの基本形と思われる形状です。
ダウンショットリグは主にその場での1点シェイクでワームをアクションさせるために使われますので、ボトムである程度の踏ん張りが利くことが望ましいかと思います。
このティアドロップ(しずく型)の形状は低重心ですので、リグの「座り」がいいことが特徴です。根掛かり回避力もありながら、いい感じの引っ掛かり感も得られる形ですね。
スティック型
スティック型は根掛かり回避能力に特化したダウンショットシンカーです。
ダウンショットリグはもともと、リグとしてはそれほど根掛かり回避力は高くありません。シンカーが根掛かりしたときはリーダーが切れるようにシンカー部分はフックよりも弱いノットで結んでおき、最悪リーダーが切れてルアーだけでも回収するという考えの「捨てオモリ式」とも呼ばれるものです。
それでも極力根掛かりを回避したいという考えで開発されたのがこのタイプの形状で、特に岩場などシンカーががっちりロックしてしまうようなシチュエーション(シェイクして使うとシンカーがどんどん隙間などに入り込んでしまう)でもほとんど根掛かりしないという特徴があります。
ラウンド型
まん丸の形をしたダウンショットシンカーです。
この形はボトムに対してどんな角度で接していても、シンカーとボトムの接地面は常に一定という特徴があり、高いレベルで一定の感度が得られると言われています。
カバーに対するスリ抜けは良くありませんが、ウィードにあえて引っ掛けてシェイクしたいときなどに向いている形とも言えます。
他にもシンカーには色々な形状のものがありますが、私的に良く使い分けているのがこの程度ですので、ここではこれくらいにしておきますね。
シンカーの重さの決め方
次に、フィールドで使うシンカーの重さはどのように決めたらいいのかということです。これも迷うところですね。
ここでシンカーの役割についてもう一度思い出したいのが、シンカーそのものは直接バスの食い気には影響しないということです。
リグしたワームの能力をより効果的に引き出してあげたり、効率よく希望の水深に到達させたりと、あくまで自分の希望の釣り方を実現させるためのものですので、シンカーの重さは、釣りをする場所の状況によって決めていきます。
その判断材料となるものは次のような感じ
水深
釣る場所の水深が深いほど重いものを使った方が効率がいい。逆にフォールを長い時間かけてアピールしたい場合は軽い方がいい。
流れの強さ
流れが強いほど重くした方が流されにくい。逆にある程度流されたいときは軽くする。
キャストしたい場所
キャストした居場所が遠いほど、または向かい風が強くて届きにくいほど、シンカーは重くした方が良い。
ボトムの質
釣る場所が岩、木材などハードボトムであるほど根掛かりしやすいため、根掛かりをしにくくしたいなら軽い方がいい。
ちょっとだけ重みを増したい
あと少しだけ重さを増やしたいときにはスプリットショットというラインに挟んでつかうシンカーを使うと取り外しができるため便利です。
リアクションで食わせたい
ナチュラルアクションではバイトして来ないと思った時は、ワームを使ったリアクションバイトを狙うことがありますが、そういう時はシンカーを重くすると動きにキレが出るため、狙ったアクションが出しやすい。
以上のようなことをあわせて考えたうえで最終的に重さを決めていきますが、私が心掛けている最も大事なことは、必要と思われる重さのなかで最も軽いシンカーにするということです。(リアクションバイト狙いの時以外)
極端な話ですが、使うシンカーの重さが釣れるバスと同じ重さだとしたらどうでしょう。おそらくバイトがあっても気付きにくくなるのではないかと思います。シンカーが重すぎると、感度が失われると私は考えています。ですので、使おうとする範囲のなかで最も軽くしたいと考えています。
しかし軽すぎるのも問題です。
軽すぎると今度は狙った水深へ到達するのが遅くなり釣りの効率が落ちるですとか、ボトムを釣りたいのにボトムを感じ取りにくい、ということになります。
ワームの性能を引き出したり、釣りの効率を上げるのがシンカーの役割ですから、それを果たせなくなるような重さに設定すると、釣果には結びつきませんよね。
私の場合ですが、シンカーの重さは何グラムにするのが正解ということではなく、自分の狙った釣りをするための最小の重さにする、ということをひとまず正解としています。

987.青テナガはよく釣れるカラーですのでお見逃しなく!
このように、シンカー選びにはいくつも考えなければならないことがあるんですね。
本当は「ここでこのワームを使って釣るなら○○グラムの○○シンカーを使えばOK!」という風に決まっていれば楽なのですが、季節や風の強さやカバーの濃さや種類など、いろんな要素によってベストな重さやシンカーの形状やリグが変わってしまうため、決められないんですよね。
バスプロさん方の取材の記事や映像を見るとシンカーのことまで細かに解説されていることもありますが、あれはその時のベストであって、絶対ではないということを覚えておいたほうがいいと思います。
シンプルなアイテムなだけに、複雑に考えて使いこなすということができますし、逆にあまり深く考えなくても結果が出てしまうのが面白い部分でもあります。
自分なりにいろいろ考えて、経験を積むことにしましょう。
もしシンカーのせいで思ったような釣果にならなかったとしても沈まないでくださいね、シンカーだけに(笑)
それではまた。
毎度ありがとうございます!
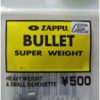
 http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
 http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
 http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
 http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
 http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...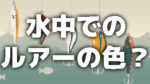
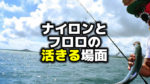
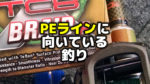



 http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...