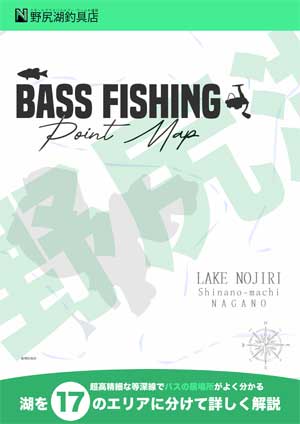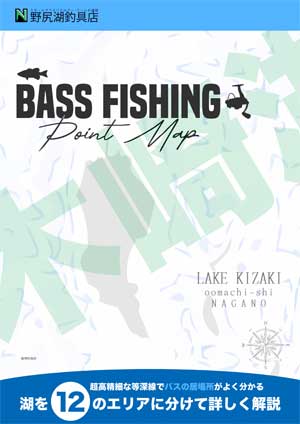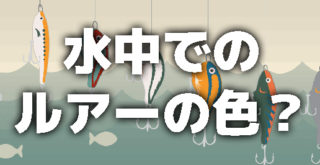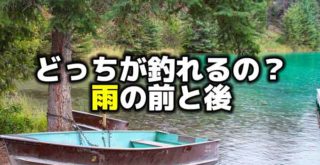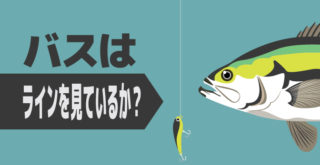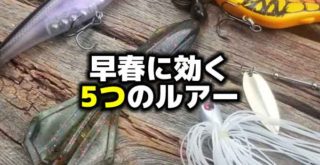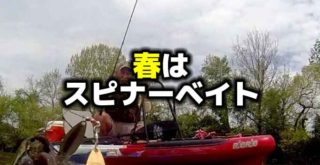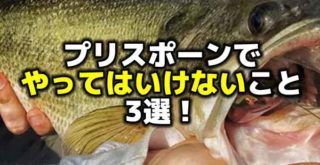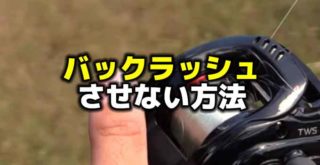沖のハンプ(地形変化)に着くバスを攻略するには

沖のストラクチャー(地形変化)の釣りというのは、アングラーによって好き嫌いがはっきり分かれると思います。この釣りが好きになれない理由はよく分かりますが、好きな人からすると、これはこれで面白い部分がいっぱいあるものですよ。
こんにちは!店長の小山です!
本日は海外サイトより、”Getting Over The Hump Of Clear Water Fishing”という記事を引用してご紹介いたします。
引用先:shopkarls.com ”Getting Over The Hump Of Clear Water Fishing”
皆さんは、沖のストラクチャー(地形変化)の釣りはお好きでしょうか。
これについては、好きか嫌いかの好みがはっきりと分かれてしまうのではないでしょうか。
バスフィッシングはもともと?本来?バスという魚の性質を考えれば、バンクを釣る釣りになるのではないかと思います。
バスの性質が何かと言えば、何かの物陰に隠れ、獲物を待ち伏せして狩りをするタイプの魚ですから、隠れ家となるものが多く獲物を追い込みやすい岸際に住むのが理にかなっているため、私たちアングラーもそれを見越した釣りをするものですよね。
ところが、そんな法則に当てはまらないバスというのも存在しています。それが、岸から遠く離れ、沖の地形変化などに居着く集団です。
これはフィッシングプレッシャーを避けて人間の少ないところを住みかとするバス説や、ベイトフィッシュを追い掛けていたら沖の地形変化に辿り着いてしまったバス説など、色々あるのですが、本当に岸から数百メートルも離れたところに集団でいたりするんですよね。
普段から岸際をメインに釣りをしているアングラーさんからしますと、目印となるものが全くない沖合の釣りになりますから、やりにくかったり、釣れる気がしなかったりするものなんですよね。
ところが、普段から沖合の釣りをしているアングラーさんですと、手元に来るボトムの感触の変化を感じただけで今にもバイトが来そうな気がして仕方がないという、全く逆の感覚を持って釣りをしているのではないかと思います。
特に沖の釣りといいますと、フィッシングプレッシャーの影響を受けやすいクリアウォーターフィールドで成立する傾向があると思いますので、なおさらに嫌なイメージが付きやすいような気もします。
私のホームの野尻湖では、岸際にそれほど執着しないスモールマウスバスがメインということもあり、沖の釣りがむしろメインとなりますので、沖の釣りには今やまったく抵抗も疑いもありません。
私個人的な考えでは、沖の釣りができたからと言って上手だとか、偉いだとかいう感覚は当然のことながら全くありません。しかし、そういう釣りも覚えればめちゃくちゃ楽しいもので、自分の釣りの幅が広がるのは間違いないと思います。
沖の釣りが嫌いという方も、そんなこと言わずに、ぜひ好きになってほしいと思っています。
ということで、今回はこんな海外の記事に辿り着いたということになるのですが、この記事は、アメリカのタックルショップ「Karal’s Bait & Tackle」のブログ記事で、沖の地形変化、主にハンプ(水中島)の釣りについて解説されています。
ぜひどちら様にも読んでいただきたいと思います。
ハンプとは?
ハンプとは、基本的には石や岩や砂からなる水中の丘のことで、バスアングラーにとって格好のポイントとなっています。 ハンプには傾斜がなだらかなものから急な斜面をもつものがあります。 ハンプにもそれぞれの個性があり、クリアウォーターに住むバスたちを攻略するためには欠かせない要素のひとつとなっています。

ハンプに対するボートポジション
メインレイクのハンプの釣りをするようなときは、ポジショニングは最も重要な要素です。 距離を置き、バスに気付かれないようにすることは、バスを釣るための重要なスキルです。 自分の存在を隠すという行動は、ハンプでのバイトが出るか出ないかの境界線となります。 まずはゆっくりとハンプに近づくこと。 ディープのハンプと言えども、早すぎるアプローチはバスを散らしてしまう危険があります。 ハンプには近付けば近付くほど、水深は浅くなるためです。 ハンプによっては水深6メートルから一気に水深60センチになるものまであるくらいです。

ハンプのどこから釣り始めるか
ボートポジションは、ハンプが傾斜し始める所から少なくとも10〜13メートル以上離れた位置に取り、ハンプの頂点に向かってロングキャストをしていき、頂点からディープ方向に向かって回収していきます。ハンプの最も浅い部分が水深1.2メートルで、深いところが5.5~6メートルだとしたら、ハンプの水深1.2メートルから水深6メートルに達するまで釣るということです。コンディションやハンプの形状にもよりますが、ハンプに着くバスはハンプの頂点かハンプまわりに着くことが多いため、できるだけ広く探るとが重要になります。
ハンプを釣るためのルアー
ハンプを効率よく釣るためには、ダウンショットなどのフィネスリグ、フロッグなども含むトップウォーター、ディープクランクを常にボートに準備しておきましょう。
寒い季節であれば、トップウォーターは選択肢から外し、1/4ozのフットボールジグをハンプの斜面に対してズル引きしていくようにします。
トップウォーター
トップウォーターは、ハンプで水面に向かってベイトフィッシュを追い込んでフィーディングしているようなアグレッシブなバスがいる水温が高く安定している時に有効です。ハンプは、バスにとっては天然の罠として機能しています。 ベイトフィッシュを探しているバスはハンプの上に陣取り、エサが来たら水面方向に追い込み、逃げ場を奪っていきます。 バスとしては逃げるベイトフィッシュの群れを水深4.5メートルから水面までではなく、水深1.2メートルから水面まで追い込んだ方が簡単であるためです。

ダウンショットリグ
ダウンショットは、ハンプに近づいてからまず最初に投げるリグです。ハンプの頂上へ投げて、足下まできっちりゆっくりと探ります。 この方法であれば広く探れると同時に、バスがハンプに対してどのような位置に着いているかも確実に知ることができます。ハンプの浅い部分にダウンショットを投げるのをためらわないでください。 ポッパーにバイトして来ない時でも、水深1メートル以内のバスがダウンショットリグのようなフィネスリグに食ってこないということはありません。

クランクベイト
ダウンショットリグのようなフィネスな釣りが我慢できないような場合は、ディープクランクでより広く探ってみてください。 浅い方へ投げたら、ボトムに向かってディープクランクをガツガツ当てていきます。 やがて水深が深くなるとクランクはボトムを離れ、ダウンショットやトップウォーターでは攻められなかったようなボトムからやや離れたところにいるバスを釣ることができます。

重要なのは季節
季節も、ハンプの釣りをするうえでは重要な側面です。ハンプが砂漠の中の丘のように隠れ家として機能せず、バスにとって本当の目的を果たせないような場合もあります。こんなハンプが機能するタイミングをあげるとすれば、水温が上昇し始めるときです。 バスが越冬するようなディープエリアと隣接するハンプなどは、ディープから上がってくるバスにとっては少ない移動距離で済みます。 バスはハンプの浅い部分を利用してシャローへ上がり、より温かいエリアやにいるであろうベイトフィッシュ、またスポーニングエリアにアクセスしようとします。
初夏はハンプを釣るのに最適な時期です。 バスはわざわざエネルギーを浪費して遠くまで移動することなく、シャローで待ち伏せるかディープで待ち伏せるかを選ぶことができます。 ブレイクラインや段差などの地形変化とは異なり、ハンプはバスにとって360度すべての方向からシャローへアクセスできるというわけです。
おまけのヒント
砂とウィードが混ざっているハンプは、ダウンショットやラバージグなどで釣るのに最適です。 石や小さめの岩でできたハンプなら、クランクベイトなどのファストムービングルアーに最適です。 砂利や岩でできたハンプは、寒い時期に水温が早く温まりやすく、バスが集まる場所となりやすいでしょう。

人間というのは不思議なもので、昨日まで嫌いで食べられなかったニンジンが、ふとしたきっかけで逆に好物になってしまうなんてことはザラにありますよね。
バス釣りにもそんなことはしょっちゅうあります。
私の話で申し訳ないのですが、私は以前、ビッグベイトの釣りがなんだか納得がいかず、釣らず嫌いだったんです。
それが八郎潟へ遠征に行くことになって、もしかしたらと思って買って持って行き、半信半疑で投げていたんです「こんなルアーいくら八郎潟でもデカくて食わないだろうなあグリグリグリ…ドバーン!」と来てからコロッと考えが変わり、どこでもビッグベイトを投げるようになってしまいました(笑)
昨日まで釣れる気がしなかった釣りが、明日から釣れる気しかしない釣りになるなんて、なんて自分勝手でご都合主義なんでしょう。でも、それが起きるから釣りってすごいですよね。自分が変わることで、見えてる世界が変わったっていうことですからね。
沖のオープンウォーターの釣りは嫌いな人からすれば本当に苦痛かもしれません。
しかし、しつこいようですが、好きな人からすればダウンショットがハンプの頂点を越えてダウンヒルになった瞬間ですとか、砂から石っぽい感触に変わった瞬間に釣れそうなイメージがドバドバドバーっとあふれてしまいたまらない感じになるんですよね。
これが昨日まで沖の釣りが好きじゃなかった人である場合も充分ありますからね、何が起きるかわかりませんよ(笑)
ちなみに、私がよく釣りをする野尻湖や木崎湖でも、この記事にあったように、初夏のころから沖の地形変化でよく釣れるようになってきます。
野尻湖であれば水中島、木崎湖であればキャンプ場沖の水中岬などが代表的な沖の地形変化になりますが、慣れていない場合は、まずそんな場所を特定するのも大変かもしれません。
そんな時は当店のオリジナルマップをご活用下さい。
紙の冊子版のマップでポイントの特徴をあらかじめ予習して知っておき、スマホ版のマップをインストールすることで、フィールド上でスマホを使って地形変化の確認をしながら釣るなんていうことができる優れモノです!野尻湖の水中島、木崎湖のキャンプ場沖の水中岬へも一発でアクセスできますよ!
地形を読み、沖のストラクチャーへのアプローチを考え、プレッシャーの少ないバスを狙って釣るというのはどんなフィールドでも挑戦してみる価値がある釣りではないかと思います。
野尻湖、木崎湖に限らず、ぜひ挑戦していくようにしましょう。
それではまた。
毎度ありがとうございます!
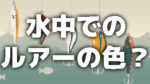
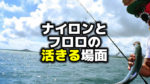
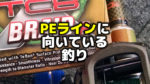



 http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
 http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
 http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
 http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...
http://www.nojiriko-fishing.com/smartphone/detail.html?id=00...